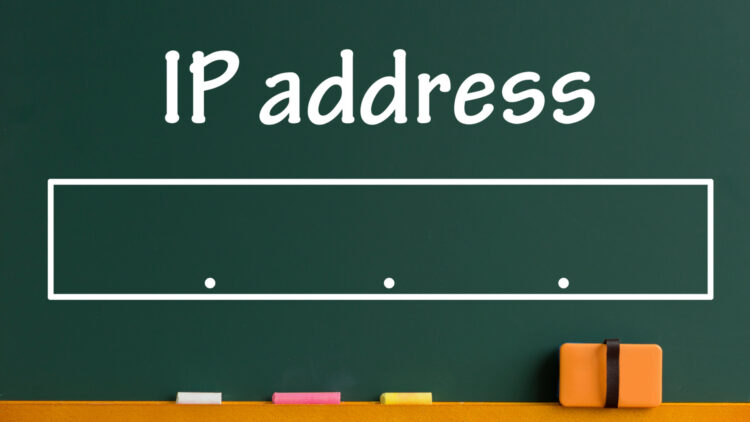2025.08.01
アドフラウドの対策方法とは?

近年、WEB広告市場の拡大とともに、広告費の一部を不正に搾取する「アドフラウド(広告詐欺)」問題が深刻化の一途を辿っています。
この記事では「アドフラウドの対策方法とは?」ということで、企業のマーケティング担当者・広告運用者のアドフラウドに対するお悩みを解決します。
アドフラウドとは
アドフラウドは「広告詐欺」「広告不正」とも呼ばれ、Web広告の表示回数やクリック数を不正に水増しし、広告費を浪費させる行為全般を指します。
主には不正クリックと不正インプレッションの2種類があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください
「WEB広告の大敵!広告成果を悪化させるアドフラウドとは?」
今回は、そんなアドフラウドの対策方法について、ご紹介いたします。
広告媒体での無効クリック除外
Google広告では、自動で無効なクリックを検出し、除外する仕組みが搭載されています。
無効クリックとは、意図的なクリックの乱用や、ボットによるアクセス、不自然な短時間での連続クリックなど、Googleが不正と判断する挙動を指します。
該当するクリックについては自動的に除外し、請求の対象からも外されるようになっているのです。
▼Googleが定義している無効クリック
・ボットや自動クリックツールなどによる不正なクリック
・同一ユーザーやIPアドレスからの複数クリック
・競合などによる、広告費かさ増し目的のクリック
▼媒体による対策
・課金対象から除外する
┗媒体が無効クリックと判断したコストは請求されません。
広告配信のデータを分析する
広告配信の数値を見ることで、ある程度の不正なユーザーを判別することが可能です。
特定の配信先サイト(ディスプレイ広告)だけ異常にクリック率が高かったり、Googleアナリティクスのリアルタイム画面で不自然な動きをするユーザーが見られた場合、アドフラウドの可能性が考えられます。
その場合、要因となっているサイトの除外や、地域・端末などのターゲティングを変更するといった対策が有効となります。
▼不信な動きの例
・同一端末やエリアからの膨大なトラフィックがある。
・ページ滞在時間が数秒単位と以上に短いアクセスが複数ある。
・短時間に複数回のセッションが発生している。
・特定のサイトにおいて異常な流入が発生している。
対策ツールを導入する
上記の2つの方法を実施すれば、自分でもアドフラウド対策が可能ですが、いくつかデメリットも存在します。
・媒体の無効クリック除外
こちらの機能ですが、その精度には限界があります。
実際には、不正クリックの80~90%が媒体側で無効と判断されず、正規のクリックとしてカウントされてしまうケースがあります。
そのため、こちらの機能だけでは防ぎきれない不正クリックが多数存在する状況となります。
・配信データの分析
こちらは、レポーティングやデータ分析など人的なチェックが必要なため、リソース面での負担が大きくなります。
さらに、何をもって不正とするかという基準が曖昧になりやすく、チェックが漏れたり、逆に正規のアクセスを誤って除外してしまうリスクもあります。
こうした手動・部分的な対策の限界を補うためには、アドフラウド対策ツールの導入が有効です。
専用ツールでは、AIや専門家による高度なデータ解析から、より精度の高い対策が可能となります。
さらに、疑わしいIPを自動で除外リストに追加してくれるなど、作業の自動化も進んでおり、担当者の工数を大きく削減できるというメリットもあります。
まとめ
今回は、アドフラウド(広告詐欺)対策の方法についてご紹介しました。
これらの対策を実施することで、無駄な広告費を削減し、広告成果の向上につなげることが可能です。
また、3つ目にご紹介した対策ツールは数多く存在するため、「どれを選べばよいか分からない」と悩まれる方も多いでしょう。
そんな方におすすめしたいのが「X-log」です。
X-logなら、不正クリックの対策を自動かつ無料で提供しているので、対策ツールの導入を検討している方は、ぜひ一度お試しください。