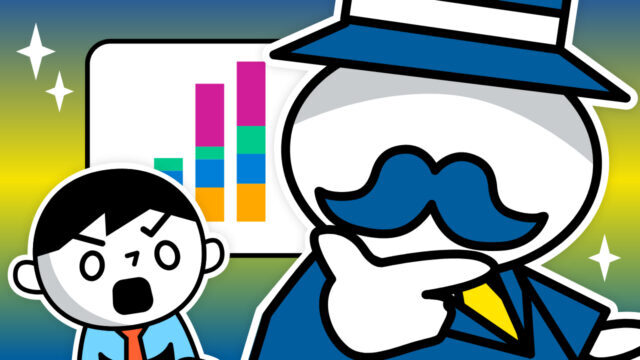2025.11.11
不正クリックとは?主な4つの手口と対策をわかりやすく解説

この記事では不正クリックの手口を4つに整理し、わかりやすく解説します。
マーケティング担当者・広告運用者が抱えるアドフラウド対策の課題解決に役立つ内容です。
目次
不正クリックとは
不正クリックとは、悪意を持った第三者が広告主の広告費を浪費させる目的で、不正にクリック数を増やす行為を指します。
WEB広告における不正クリックはもはや一過性の問題ではなく、広告効果を脅かす構造的なリスクです。
広告費の損失だけでなく、成果データを歪めることで正確な効果検証を困難にしてしまいます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
不正クリックとは?仕組みと防止策を徹底解説
本記事では、不正クリックの代表的な手口を4つに分類して詳しく解説します。
不正クリックの4つの手口
現在、代表的な不正クリックの手法としては以下の4つが挙げられます。
①手動による不正クリック
②ボットによる自動クリック
③端末養殖場(デバイスファーム)
④クリック洪水(クリックフローティング)
それぞれの特徴を見ていきましょう。
① 手動による不正クリック
最もシンプルな手口が、手動での不正クリックです。
競合他社や悪意のある個人が、特定の広告を繰り返しクリックして広告費を浪費させる行為です。
特に検索広告などクリック単価の安い領域ほど被害を受けやすく、
「クリック数は多いのにコンバージョンがない」「特定キーワードでクリック率が異常に高い」場合は要注意です。
② ボットによる自動クリック
次に多いのが、プログラム(ボット)による自動クリックです。
これはソフトウェアが自動的に広告をクリックし、短時間で大量のトラフィックを発生させます。
近年はAI技術を用い、人間の挙動(スクロール・滞在時間・ページ遷移など)を模倣する擬似人間型ボットも増加しており、
従来の検知方法では発見が難しくなっています。
③ 端末養殖場(デバイスファーム)
より巧妙で検知が難しいのが「デバイスファーム」と呼ばれる手法です。
大量のスマートフォンやPCを物理的に並べ、人間や遠隔操作でクリックやインストールを行う仕組みです。
モバイルアプリ広告で特に深刻で、インストール数は多いのに起動率や継続率が異常に低い場合、デバイスファームの被害が疑われます。
アプリ内イベントやサーバーサイド計測で「実際の利用行動」を検証することが効果的です。
④ クリック洪水(クリックフローティング)
近年増加しているのが「クリック洪水(クリックフローティング)」です。
これは一度発生したクリックを、他媒体やプレースメントで再利用・偽装し、データ上だけクリック数を水増しする詐欺的手法です。
実際のアクセスは増えていないのに、レポート上のクリックが急増している場合は、この手口が関与している可能性があります。
不正クリックの問題点
これらの不正クリックに共通しているのは、広告主が気づきにくいという点です。
クリック数やCTR(クリック率)が良好に見えるため、成果が出ているように錯覚してしまうことがあります。
しかし、その裏では実際のユーザー行動を反映していないノイズデータが混在しているかもしれません。
重要なのは「クリック数」ではなく「クリックの質」を見ることです。
ユーザーの行動指標(滞在時間、CV率、離脱率など)を組み合わせて分析し、不自然な動きを早期に発見できる仕組みを整えましょう。
また、GoogleやMetaなどの自動検知任せにせず、外部の不正クリック対策ツールを導入して自社で防御体制を構築することも有効です。
まとめ
今回は不正クリックの代表的な4つの手口について解説しました。
不正クリックは種類も多く、気付きにくいことから、「被害に遭う前に備える」意識が重要です。
不正クリック対策を、今すぐ始めましょう!
X-logは、広告主が手軽に導入できる不正クリック対策ツールです。
広告費を守り、健全なマーケティング環境を維持するために、ぜひ一度ご検討ください。
⇓
【無料で始める】不正クリック対策ツール X-log 無料申し込みはこちら